2016年9月15日 第38号
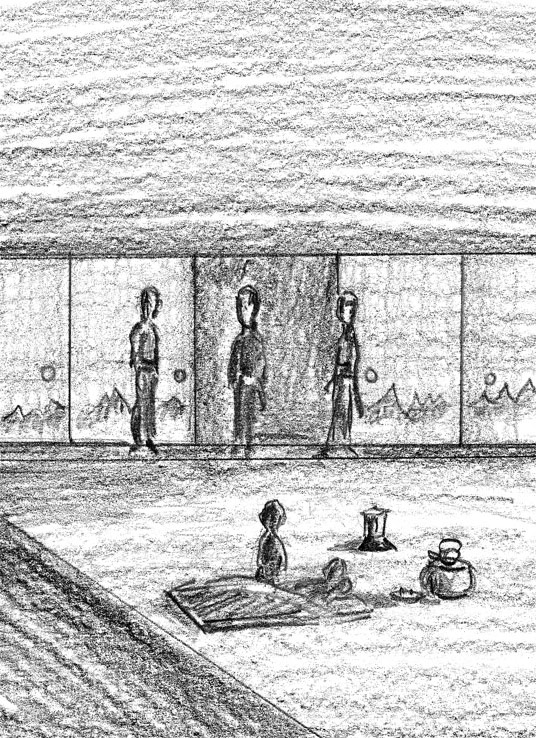
イラスト共に片桐 貞夫
シズノの身体が硬直した。
女がいる。かすかに見える白いものは女の顔に違いない。シズノはひきつる片腕で身体を起こした。
「ううらめしー…」
女の顔がある。たしかに女の顔がある。
「わちしうらみをなんとすぞー」
女のほほが割れている。真っ赤に裂けて血が噴き出ている。
「よくよくみーやれこのかおみやれ」
ぞっとするような低い声である。
「みーやれこのかおよくよくみやれ」
八重である。女は八重であった。死んだはずの八重が、幽霊となってほほから血を流しているのである。
「うらめしこのかおわすれしやー…」
シズノは動けない。声を出すこともできない。凄惨な女の血だらけの顔は正視し難いが、眼だけは意に逆らい、眼球いっぱいに開いてままならない。
「よくよくみーやれうらめしやー、てまえのつけたきずあとみーやれ」
幽霊は、なぜか闇の中に浮き上がり、おし殺したような声で呪いごとを繰り返す。シズノの耳だけに聞こえるような低く冷たい声である。
「きってやる。こよいこのときうらめしい、てまえのほほをきりさいて、とわのうらみをはらしてやる」
シズノの口から声が出ない。隣の部屋で寝ているはずの吉藏を呼ぼうと思うのであるが、舌が凍りついて動かない。
幽霊の八重が枕元に近づいてきた。両のほほが真っ赤に裂けている。握っていた短刀の先をシズノのほほに近づけた。
「かおをきられたおんなのうらみ、こどもころしたおんなののろい、きってやる。このほっぺたをきりさいて、とわのうらみを…」
色子が目を覚ました。シズノの肉体の硬直にただならぬものを感じ取ったのだろう。顔をまわした。血だらけの幽霊の顔がそこにあった。
「わっ!」
少年がシズノの身体にしがみついた。
その時、隣の部屋で人の動く音がした。唐紙が開いた。灯りがついた。三人の男が立っている。あおくびこと、立願寺の吉藏と子分の二人が灯りを背に、長どす片手で影をつくっている。
「いらしゃいましたな」
いかり肩で大柄な吉藏が、期待を裏切るような高い声で言った。
「待ってたぜ」
吉藏を中に三人が部屋の中に入ってきた。そして、ろうそくの一つを幽霊女に向けた。女はシズノの枕元で片膝をついている。
「幽霊たあ大笑いだぜ」
幽霊は上半身は無地の白。下半身は黒で染めた袷を着ている。わずかな灯りでも、顔と白地は引き出るが、下半身は闇に溶け込む。足がないように見える。両ほほの赤い傷も、紅で装ったものであった。
吉藏が続けている。
「てめえーは幽霊なんかじゃねえ。八重でもねえ。誰だ。誰なんだ」
幽霊の女は動かない。右手に持つ短刀の刃先を近江屋シズノのほほにつけ、その命は女の掌中にある。
「似ちゃあいるが八重じゃあねえ。八重は死んだ。八重はおれがたたき斬ったんだ。幽霊を真似やがった八重を殺し、簀巻きにして柏尾の魚に食わしたのは、このおれが直々にやったんだ。誰なんだてめーはいってー」
「うっ」
幽霊女が吉藏をにらんだ。血で模した残忍な形相である。
吉藏がまた一歩前に出た。
「誰なんだよ」
「…」
「てめーはいってー誰なんだ。なんの恨みで幽霊なんかになりやがったんだ」
「いと」
しばらくしてから幽霊が言った。はじめて人間としての声を出した。
「なんだとー、…イト?」
「八重の娘だ」
イトとは女の名前である。八重の娘だと言っている。しかし声調は男のものであった。
「八重の娘が、てめーらを殺そうと地獄の底からやってきたんだよ」
腹の底から出てくるような背筋の冷たくなる声である。
「なんだと。八重の娘だと? そりゃあでたらめだ。八重に娘がいたってえーことは聞いたことがあるが死んでるんだ。八重の娘ってーのは八重に喉をぶっ刺されて死んだんだ」
「だから、地獄の底からやってきたって言ってるじゃねえか」
幼いころから指切りし、慕い慕われた惣次郎が、親に強いられて近江屋に婿に行くと、八重は我が身のいたし方ないことを知った。
(続く)












