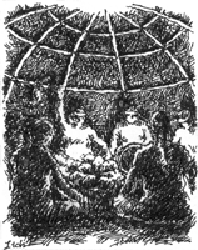
〈前回より続く〉
この儀式をとりしきる人と思われる長老の祈りが始まった。今日のこの儀式が無事取り行われることの「万物の創造主」への感謝の言葉が 分程続く。居並ぶ人達は、身じろぎ一つしない。厳粛な儀式のスタートである。やがて長老が大きな声でテントの外にいる人に儀式のスタートを告げた。
入口の毛布がはねあげられ、外で燃えさかっている焚火の中から真っ赤に燃えた大きな石がスコップに一個ずつ乗せられて、テントの中に運び込まれる。テントの中央にある窪みに置かれた石は全部で10個程。 溶岩のように赤く炎を上げて燃えている。はね上げられた入口の毛布がおろされ、テントの中の熱気は信じられない程の早さでグングン上がってくる。
長老の合図で円形のリングに皮を張った太鼓が打ち始められる。その音はドンドンドンドンと云う単調なリズムでありながら力強さと何かの始まりを感じさせるのに充分であった。密閉されたテントの中でのこの太鼓の音は腹の中まで響くような迫力があり、真っ暗闇の中で次第に自分の気持が日常のわずらわしさから切り離されてゆくような不思議な錯覚を覚える。
もう一度長老の祈りがあり太鼓の響きが止った。一瞬静寂が流れる。車座の中央に置かれた焼けた石は、テントの中の10人の顔を真っ赤に照らし出し、その熱気たるや街中のサウナ室もかなわない位。思わず山積みされた石から顔をそむける程で、汗がいつの間にか体中から吹き出しているのが解る。隣りに座ったB氏は少しでもその熱さから逃れるため、とうとう横になった様子。最後までこの熱さに自分が耐えられるかどうか心配になって来た。恐らく140度はあると思われ、今にも髪の毛が燃えだしそうな気配を感じるものの、 目を閉じ、歯を食いしばって必死で背スジを伸ばす。
居並ぶ先住の人達の創造主に捧げる感謝のスピーチが始まった。
一人一人汗を額からしたたらせながら2~3分の言葉を述べる。それは神への報告であり感謝の言葉でもあった。このスピーチの間、太鼓の音は小さいながら正確なリズムで地鳴りのように打ち続けられ、この太鼓の音が人と神とをつないでいる唯一の媒体のように感じられるのだった。
一人の祈りが終ると車座にあぐらをかいて座った人々の中から、オウーッ、ヒャーッ、そしてホホホ・・・!!と云う大きな声があがる。儀式が次第に盛り上ってくるのが感じられる。この叫び声はどこかで聴いた憶えがある。そう、考えてみたら昔見た西部劇の映画の中で、インディアンが幌馬車を襲う時の声と同じであることに気がついた。しかし、ここでは同意を表わす意味のように思われる。
長老が焼けた石にヒシャクで水をかける。ものすごい湿気と共にテントの中の温度が一気に上がり、呼吸が苦しくなって目眩がする。鹿の角で石をひっくり返す。火花が散って石の赤く燃えた部分が上になる。タバコの粉と香料が、火にふりかけられ、鹿の角がこげる動物質の匂いと香料が燃える匂いが充満する。排気など一際できない密閉された狭い空間での、この熱気と物が燃える匂い。それに間断なく打ち鳴らされる遠い祖先に語りかけるような太鼓の響きは、日常私達が出合うことのない異様な体験以外の何物でもなかった。
神に捧げるスピーチは、時計廻りに進んだ。私の隣に座った若いネイティブが、ホッ!と云うような声で私をせきたてている様子。左隣のB氏が「何でもイイから・・・」と苦しそうな声でつぶやく。どうやら私が神に祈りをささげる番になったらしい。正直なところ自分も何かの祈りを捧げることになるとは夢にも思っていなかったので、さてどうしたものかと熱気の中で頭の中が真っ白になった。今迄何かに頼って祈りを捧げる等と云う経験は自分にはなかった。
云い方を変えれば自分が神様であり、この世の中は自分を信じて自分のために自分が努力をしなければいけないものだと思っていた。だから突然、神様に何かを話せと云われても慌てるばかりで汗も一瞬止ってしまう程だった。まして英語である。こんなパニックは久しぶりのことではあったが、しかし今更あわてふためいても致しかたなし・・・と、腹を決めてみた。腹が座ると今度はフッとしゃべってみたいことが頭に浮んだ。
そうだ、あれはラッキーだった。
もしかしたら、あの時自分の命は終っていたのかも知れないと思った。
3年前の脳溢血のことだった。
しかし下手な英語でそれを話せる自信はなかった。
笑われてもイイヤ、笑いたい人は笑ってくれ・・・と、そんな気持ちでしゃべり出した。
〈次回に続く〉
2006年11月16日号(#47)にて掲載












