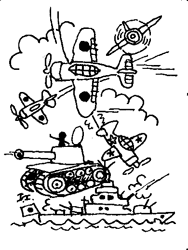
東京・神田にあるビルの小さな一室を借りて、ささやかなデザインの仕事を始めた。一九七〇年、念願の自立だった。
お金もなければスタッフもいない心細いスタートで、あるのは仕事に対する情熱だけ。戦後二十五年が過ぎていた。
そんなある日、全く知らない人からの一本の電話があった。デザイン依頼の電話で、造形工場を営む方からだった。
グラフィック・デザインに興味が薄らいで、立体的なデザインに傾いていた私は「一体、何のデザインを頼まれるのだろう…」と期待しながら電車をのり継いで小田急線の小さな駅に降り立った。
当時まだ開発もなかばだったその一帯は駅周辺を離れる程に田畑がひろがって、神田と云う繁雑な場所で仕事をしていた私には同じ東京とは思えないほど、のどかな風景だった。もう夕暮れだった。
しばらく農道を歩いてお会いする約束をした電話の工場を探した。
多分この辺だと思って歩いていたら大きな背の高い金網で囲われたグラウンドがあって、そのフェンスに小さな子供達が大勢つかまって近づいてゆく私を見ている。
恵まれない子供達の養護施設だと云うことをアトで知った。やがて目指した工場についた。小さな平屋のその工場は外から見ても何を造る工場なのかわからなかったが樹脂特有のアルコールのような臭気が鼻をつく。
工場主は加藤さんと云う私より五つ六つ年上の小柄な男性だった。応接間に通して下さった加藤さんは見るからに仕事中と云った作業衣姿で、あちこち塗料だらけだった。他のスタッフも帰ったあとでお一人だった。
加藤さんがお茶をいれて下さる間私は応接間の壁に掛けられた何枚かの写真を漠然とながめていた。
それらの写真はどれも古びて茶色に変色している。更によく見ると旧日本陸軍の戦闘機であり、飛行メガネをかけた搭乗員の写真だった。その他の写真はない。
いくら回転の鈍い私の頭の中でも「連想」が始まった。加藤さん。旧日本陸軍の戦闘機「隼」そしてその搭乗員。
「もしかして…」仕事の打ち合わせはアト廻しにして私はお茶をもって表れた加藤さんに吃りながら聴いた。
私の勘は適中していた。
加藤さんの父君は私が幼年期を過ごした太平洋戦争中、その最前線で名機「隼」の編隊を組んで勇名を馳せた「加藤隼戦闘隊」の加藤隊長であった。
♪エンジンの音、轟々と隼はゆく…。歌に唄われた方だ。
大戦末期、幼かった私にとってワラ半紙や路上に這いつくばってロウセキで絵をかく位しか楽しみは無かった。それもことごとく戦車や空中戦の絵。そう云う時代だった。
戦後六十五年も過ぎた今、若い方たちには多分、理解しがたい事だと思うけれど、当時戦争の善し悪しは別にして国の存亡に命を賭して恋人や子供達や親や老人のために自己を犠牲にした数え切れないほどの若者がいたことは、まぎれもない事実である。
そんな時代に幼年期を過した私にとって自分達を守る為に己の青春を捨てて戦場に赴いた若い兵士達の気持ちを思う時、それは永劫の痛みなのだ。
ご存知でしたか…。ポツリポツリ話しだした加藤さんの言葉は私の胸を打った。
戦闘機乗りのご子息として幼年を過した加藤さんは当然のことのように飛行機に興味を持ち、ひいてはいろいろな乗物が大好きな少年に育った。
そして現在のお仕事は遊園地の遊具としての乗物それもとりわけ空中をワイヤーに吊られて飛ぶ飛行機を造っておられて私が依頼されたのは、その子供が乗る飛行機のデザインだった。
加藤さんの工場を出て、夕陽が沈む田園を駅の方に向かって歩く私の胸は、ある感慨で満ちて息苦しい程だった。
それは一種の感動に近いものだった。もう、とうに亡くなられた加藤さんの父親は命を賭して私達を守って下さった飛行士であり、そのご子息が毎日やさしかった父親を思い浮かべながら平和な時代とは云え遊具としての飛行機を造っておられる。そして私はそれを微力ながらお手伝いできる。それは私にとって自分を守って下さった方に対するせめてもの恩返しに似た感情でもあった。
帰りの道で又、子供達の施設の前を通った。子供達がフェンスにかけ寄ってくる。
身寄りのない子供達にとっては、誰かが尋ねてきてくれることが何よりの心のなぐさめになるのだろう。私もその訪問者の一人と思われた筈だ。そう思うと金網につかまって私を見る子供達の目がいじらしくて辛かった。
そして、この子供達と父親を偲びながら飛行機を造り続ける加藤さんが私の頭の中で重なり何かが胸にこみ上げた。暗くなった農道に佇ずんだ私の頬を不覚にも熱いものが伝わった。
2010年4月22日号(#17)にて掲載












